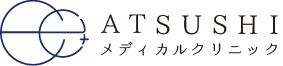ストレスが腸に与える影響
静岡県浜松市のATSUSHIメディカルクリニック、院長の鈴木淳司です。
私たちの腸は「第二の脳」とも言われ、感情やストレスと深くつながっている臓器です。
たとえば、緊張するとお腹が痛くなったり、プレッシャーが続くと便秘や下痢になったりした経験がある方も多いのではないでしょうか。
このような現象は「腸脳相関」と呼ばれる仕組みによるもので、脳と腸が神経ネットワークを通じて密接に連携していることを示しています。
ストレスを感じると自律神経のバランスが乱れ、それによって腸の動きや血流、免疫機能にも影響が及びます。
特に慢性的なストレスは、腸内環境の悪化につながり、悪玉菌が優位になることで消化機能にも悪影響を与えます。
その結果、腸が不調になるだけでなく、気分の落ち込みや不安感が強くなることもあり、まさに「こころ」と「腸」はお互いに影響を与え合っているのです。
日々のストレスケアは、心の健康だけでなく腸の健康を保つためにもとても大切です。
消化器内科では、内視鏡や血液検査などの身体の検査に加えて、こうした心と体のつながりにも配慮した診療が行われています。
過敏性腸症候群(IBS)とはどんな病気?
朝の通勤や通学の準備をしていると突然お腹が痛くなる、トイレに何度も行きたくなる、あるいは日によって便秘と下痢が入れ替わる。
このような便通の不安定さを感じている方は、決して少なくありません。
過敏性腸症候群(IBS)は、検査では明らかな異常が見つからないにもかかわらず、腹痛や便通の異常が繰り返し現れる病気です。
特徴的なのは、ストレスや緊張によって症状が強くなる傾向があること。
会議や発表、外出前といった特定の場面でお腹の不調が出やすく、仕事や学業、日常生活に大きな支障をきたすケースもあります。
IBSの背景には、腸の運動機能や知覚が過敏になっている状態、自律神経の乱れ、腸内環境の悪化などが関係していると考えられています。
消化器内科では、薬物療法だけに頼らず、食事のアドバイスや生活習慣の見直し、必要に応じてストレスマネジメントも含めた包括的なケアが行われます。
「ただの気のせい」と片づけず、患者様のつらさに寄り添うことが、IBS治療の第一歩です。
また、「自分の症状に名前がついた」と安心される方も多く、診断を受けること自体が心の支えになることもあります。
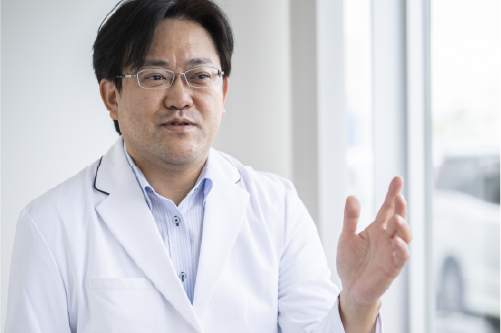
お腹の不調を気のせいで終わらせないために
「病院で検査しても異常がなかった」と言われても、日々感じているお腹の不調は現実に存在し、生活に大きな影響を与えます。
そのようなとき、「気のせいかも」と思ってしまったり、「自分が弱いせいだ」と自分を責めてしまったりする方も少なくありません。
しかし、腸は感情にとても敏感な臓器です。
ストレスや不安が腸の動きに影響を与えることは、医学的にも明らかになっています。
消化器内科では、目に見える異常だけでなく、患者様の生活背景や心理的要因にも目を向けた診療を大切にしています。
「きちんと話を聞いてもらえた」「気持ちをわかってもらえた」と感じるだけで、症状が和らぐことも珍しくありません。
お腹の不調は、こころのバランスが崩れているサインになることもあります。
だからこそ、気のせいと片づけず、専門的な視点でケアすることが、心身の安定につながるのです。
消化器内科は、体と心の両面から患者様を支える場所です。
お腹の不調が気にならない毎日を過ごせるよう、しっかりとサポートしていきます。
まとめ
ストレスと腸の関係は、見えにくいものですが、確かに存在しています。
消化器内科は、こうした目に見えない不調や心の声にも寄り添う診療を大切にしています。
過敏性腸症候群のように、検査では異常が出ない症状に悩む方にとって、「気のせいではない」と認めてもらえることは、大きな安心につながります。
腸の健康を整えることは、こころの安定にもつながるのです。
食事や生活習慣の見直し、ストレスマネジメント、そして医療者との信頼関係が、症状改善への道を支えます。
「こころと腸のケア」は、患者様の生活に寄り添う医療の形のひとつです。
消化器内科では、確かな知識とやさしさをもって、今日も誰かのお腹と心を支えています。
気になる症状があるときは、どうか一人で悩まずに相談してみてください。