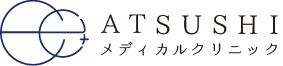痔とはどんな病気か
静岡県浜松市のATSUSHIメディカルクリニック、院長の鈴木淳司です。
「痔」とは、肛門に関するさまざまな病気を総称する言葉で、いぼ痔、切れ痔、痔ろうの3種類に大別されます。
肛門周囲に出血や痛み、膿が溜まるなどの症状が現れることが特徴です。
多くの人が「痔=出血やいぼ」といった印象を持っているかもしれませんが、実際にはもっと多様な症状があります。
いぼ痔は、肛門周囲にいぼができる症状で、さらに外にできるものを「外痔核」、内側にできるものを「内痔核」と呼びます。
切れ痔は、便が硬いときや無理にいきんだときに肛門の皮膚が切れてしまう症状です。
そして、痔ろうは、細菌が肛門周囲の皮膚に感染し、膿が溜まることで、肛門と直腸を繋ぐトンネルができてしまう病気です。
症状としては、肛門周囲の痛みや腫れ、出血などが現れます。
痔は男性に多いというイメージがあるかもしれませんが、実際には女性にもよく見られ、若い人や妊婦さんにも症状が現れることがあります。
特に女性の場合、「恥ずかしい」「誰にも相談できない」と思っていることが多いため、密かに悩んでいる方も少なくありません。
年齢や性別を問わず、多くの人が悩んでいる病気が痔なのです。
痔の治療方法

痔の治療は、主に薬物療法と手術療法に分けられます。
薬物療法では、痛みや出血を抑えるために、塗り薬や座薬が使用されます。
また、便秘や下痢などによって肛門に負担がかかることで症状が悪化するため、便通を調整する薬を併用することもあります。
その他、長時間座っていることや重いものを持つこと、過度の飲酒といった生活習慣が痔を悪化させることもあるため、生活習慣の見直しも大切です。
薬物療法は、消化器内科で行うことができます。
しかし、薬による治療で症状が改善しない場合や、何度も繰り返し症状が現れる場合には、外科的な手術を検討することがあります。
消化器内科でできる痔の治療

肛門に関する症状は、恥ずかしくてなかなか受診できないという方も多いかもしれません。
しかし、肛門からの出血や痛みがある場合、それが必ずしも痔によるものとは限りません。場合によっては、大腸がんや他の病気が隠れていることもあるのです。
そのため、症状が続くようであれば、市販薬を使い続けても改善しない場合は、早めに医師の診断を受けることが重要です。
消化器内科では、肛門からの出血がある場合、大腸がんなどの病気を排除するために、大腸カメラ(内視鏡検査)を行います。この検査を通じて、痔以外の病気が隠れていないかを確認します。
大腸がんなどが否定され、痔と診断された場合は、その症状に合った治療を行います。
いぼ痔の場合、いぼが肛門の中に納まっている場合や、飛び出してもすぐに戻る場合、または痛みがない場合には、軟膏や座薬を使って症状を軽減させることができます。
さらに、便通をコントロールすることや、重い物を持たないようにするなど、生活習慣の改善も推奨されます。
切れ痔の場合、肛門の皮膚に切れ目が入っている状態ですが、その傷が浅い場合は、軟膏や座薬で傷の治癒を待ちながら、便を柔らかくする薬を使用して肛門にかかる負担を軽減します。
しかし、いぼ痔や切れ痔で治りが遅い場合や、痛みが強い場合には、手術が必要になることもあります。
痔ろうの場合は、膿が溜まって肛門周囲に穴が開いてしまっている状態であり、内科的な治療では治すことができません。
この場合、消化器外科や肛門外科での手術が必要となります。
まとめ
多くの人が痔の治療には手術が必要だと考えがちですが、実際には内科的な治療でも症状を改善できることが多いです。
薬物療法が有効な場合、まずは内科での治療を試み、症状が改善しない場合に外科的な手術が検討されます。
手術を行う際も、内科的治療で症状を軽減させてから手術を行うことで、身体への負担が少なくなります。
また、痔と思い込んでいた症状が実は別の病気だったということも少なくありません。
肛門からの出血や痛みが続く場合は、恥ずかしがらずに早めに医師の診断を受けることを強くおすすめします。